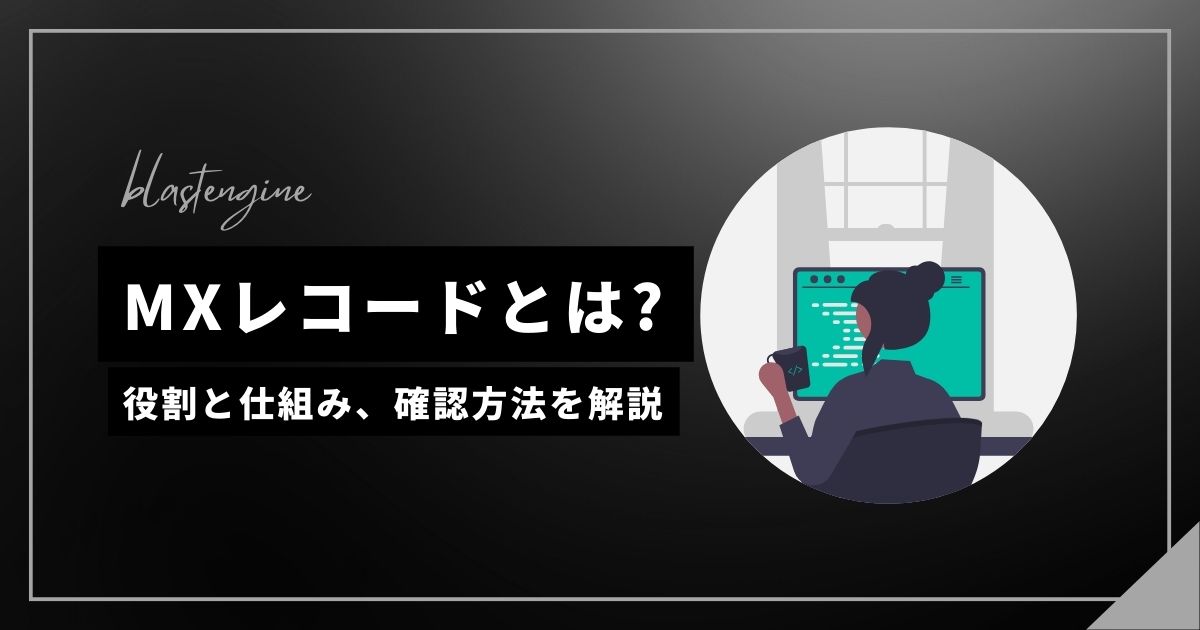メールサーバーをクラウド化するメリット・デメリット、方法、手順を詳しく解説
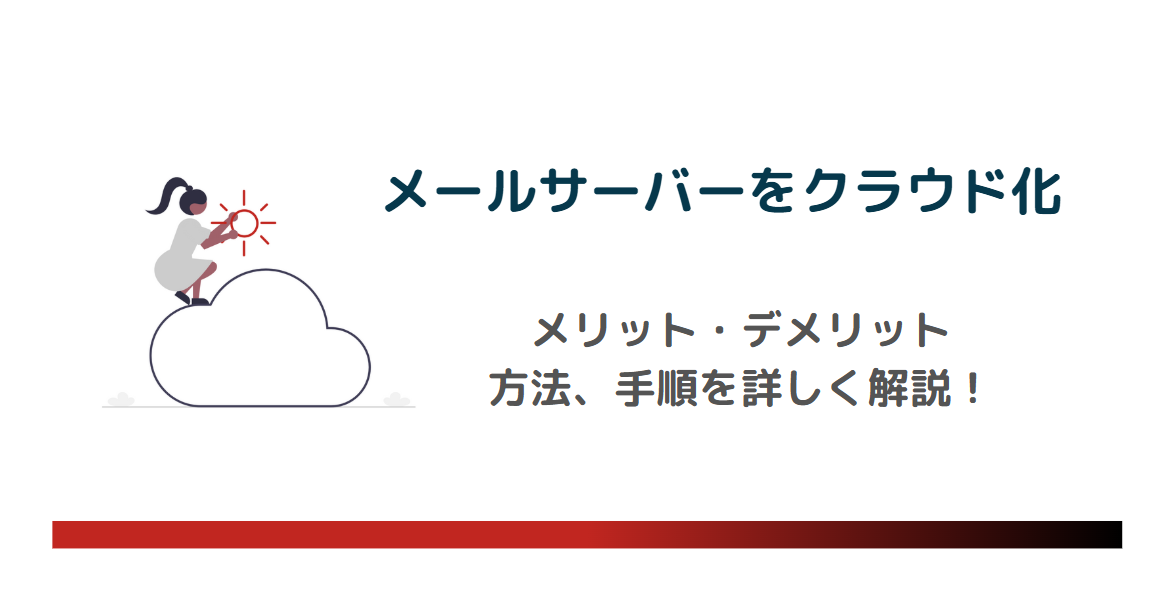
インターネット環境の進化やリモートワークの普及に伴い、「メールサーバーをクラウド化」する企業が増えています。オンプレミス型(自社運用)のメールサーバーからクラウドへ移行することで運用負荷を軽減し、コストを抑えたり、働き方の多様化に対応できる点が大きな魅力です。
一方で、クラウド化にはコストがかさむ場合や自由度の制限、ベンダー依存などの懸念もあり、決断に迷う企業は少なくありません。実際、多くの企業が「クラウド化すれば本当に安くなるのか」「セキュリティ面は大丈夫なのか」「移行作業はどれくらい大変か」など、さまざまな疑問を抱えています。
本記事では、「メールサーバーをクラウド化」するメリット・デメリットから、移行方法や手順、コストの考え方までわかりやすく解説します。これからクラウド移行を検討する企業の方にとって、失敗しないためのポイントを詳しくお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
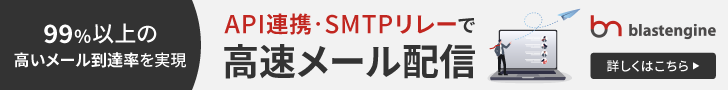
目次
メールサーバーのクラウド化とは
メールサーバーのクラウド化とは、従来オンプレミス型(自社運用)のメールサーバーを、クラウド上のサービスへ移行することを指します。自社でメールサーバーを保有せず、クラウドのメールサービスを利用する形態も含まれます。
クラウド化によって企業はサーバーの保守や運用業務から解放され、本来注力すべきビジネスにリソースを集中できるようになるでしょう。セキュリティ対策や運用コスト削減の観点からも、近年はクラウドへの移行を選択する企業が増えています。
メールサーバーをクラウド化するメリット
メールサーバーをクラウド化することで、さまざまなメリットが得られます。代表的なものを以下で詳しく見ていきましょう。
コストや手間を削減できる
オンプレミス型の場合、サーバー本体やOS、関連ソフトウェアの購入、ネットワークの構築、インストールなどが必要です。さらに、サーバー運用には電力費だけでなく、定期的なメンテナンスやアップデートも伴います。一方、クラウド化すれば自社でサーバーを構築する必要がないため、以下のようなコストや手間を削減できます。
- サーバーの購入費用や設置費用
- 保守・管理の人件費
- ハードウェア障害対応にかかる工数
- アップデート作業やセキュリティ対策の負担
ベンダーがサーバーの管理や運用を代行するため、専門知識を持つ担当者の人件費も大幅に削減できるでしょう。
すぐに利用できる
オンプレミス型の場合、規模や構成にもよりますが、構築には数日〜数週間を要するのが一般的です。
クラウドサービスであれば、ベンダーがあらかじめ構築・最適化したシステムを利用する形態のため、契約手続きを終えれば即日または数日以内に利用を開始できます。比較的シンプルな初期設定だけでメール環境が整うため、専門知識がそれほどない担当者でもスムーズに導入を進められる点も大きなメリットです。これにより、機会損失の回避や競争優位性の確保にもつながるでしょう。
場所を問わず利用できる
クラウドサービスを利用すればインターネット経由でどこからでもアクセスが可能です。オンプレミス型の場合、特別な設定をしなければオフィス外からのアクセスは難しいケースが多いでしょう。
しかし、クラウド化することでインターネット環境さえあれば遠隔地でもオフィスと同様に利用でき、リモートワークや出張先でのメール対応もスムーズになります。
拡張性が高い
クラウドサービスは、必要に応じて簡単にスケールアップやスケールダウンができる拡張性の高さが魅力です。オンプレミス型の場合、ストレージの増設や性能の高いサーバーへの移行には、物理的な交換作業や多額の費用、場合によっては一時的なサービス停止が伴います。
一方、クラウドサービスでは契約内容の変更だけでリソースの増減が可能です。例えば、不要になった分は契約を戻すこともでき、従量課金制のサービスを活用すれば無駄なコストを抑えられるでしょう。
保守管理を自社で行う必要がない
クラウドサービスを利用することでサーバーやソフトウェアの管理、メンテナンスはすべてベンダーが担います。ハードウェアの故障対応やソフトウェア更新などの手間から解放されるため、担当者は本来の業務に専念できるでしょう。結果として、業務効率の向上や人的リソースの最適化につながります。
メールサーバーをクラウド化するデメリット
クラウド化には多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべきデメリットも存在します。ここでは、メールサーバーをクラウド化する際に考慮すべきポイントを解説します。
コストが高くなる場合もある
機器の購入やサーバー構築、保守・管理にかかるコストを削減できる可能性はありますが、クラウドサービスが無料というわけではありません。多くの場合、月額や年額で利用料が発生し、ユーザー数や配信数が増えるほどコストが高くなります。
そのため、利用規模や利用期間によっては、オンプレミス型の方が総コストを抑えられるケースも珍しくありません。特に長期間かつ大規模に運用する場合には、クラウド化を慎重に検討する必要があるでしょう。
自由なカスタマイズは難しい
一般的にクラウドサービスは多様な企業が利用できるように標準的な機能を備えています。そのため、自社独自の業務に合わせた細かなカスタマイズや、特殊なソフトウェアとの連携は難しい場合が多いです。もちろん、API連携を提供するサービスもありますが以下のような課題があります。
- 連携できる範囲や仕様がサービスごとに異なる
- カスタマイズには追加費用が発生することがある
- 想定以上にコストが膨らむ恐れがある
自由度の高いカスタマイズを重視するなら、オンプレミス型の方が適している場合もあるでしょう。
自社にノウハウが貯まらない
クラウドサービスではサーバーの保守や管理をベンダーが担ってくれる点がメリットですが、その反面、メールサーバー運用に関するノウハウが自社に蓄積されにくいというデメリットもあります。
例えば、システム障害が発生した場合でもベンダー任せになることが多く、自社内で原因を究明したり、トラブルシューティングを行ったりする機会が少なくなります。将来的に再びオンプレミス型へ戻す場合や高度なシステム連携が必要になる場面では、社内に専門知識を持つ人材が不足するリスクがあるでしょう。
セキュリティ対策がベンダーに依存する
クラウドサービスを利用する際はシステムの運用やデータ管理、セキュリティ対策など、多くの面でベンダーに依存することになります。しかし、ベンダーごとにセキュリティレベルには差があり、中には不正アクセスや情報漏えいのリスクが高まるサービスも存在します。
そのため、クラウドサービスを選ぶ際には提供するベンダーの信頼性やセキュリティ対策の内容をしっかりと確認することが大切です。
メールサーバーをクラウド化する方法
ここではメールサーバーをクラウド化する方法について解説します。クラウド化する際は、大きく分けて IaaS を使う方法と、クラウドメールサービス(SaaS)を利用する方法があります。
IaaSでメールサーバーを構築する
IaaS(Infrastructure as a Service)とは、ネットワークやサーバーなどのコンピューティングリソースをインターネット経由で提供するサービスです。代表的なサービスとしては、以下のようなものがあります。
- Amazon Web Services(AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform(GCP)
IaaSを利用する最大のメリットはオンプレミス型に近い自由度でサーバーを構築・運用できる点です。OSや利用するソフトウェアなど、自社の要件に合わせて細かくカスタマイズでき、ハードウェアの調達や物理的な運用も不要です。
ただし、OSのセットアップやメールサーバーソフトウェアのインストール、各種設定など、運用管理は引き続き自社で行う必要があります。そのため、サーバー運用の専門知識を持つ担当者が求められ、運用負荷はSaaSに比べて高めです。また、障害が発生した際の原因調査や対応も自社の責任範囲となるため、運用体制の整備が重要です。
クラウドメールサービス(SaaS)を利用する
クラウドメールサービスとは自社でメールサーバーを構築・運用することなく、Webブラウザや専用アプリを通じてメールを送受信できるサービスを指します。これはインターネット経由でソフトウェアを利用する SaaS(Software as a Service) の一種です。
代表的なサービスにはMicrosoft 365やGoogle Workspaceなどがあります。これらのサービスは、自社のドメイン名を利用してメールを運用できるように、メールサーバーを提供してくれます。ホスティングサービスも、広い意味ではクラウドメールサービスの一種といえるでしょう。ビジネス用途を想定しているため、個人向けメールサービスと比べると以下の点で優れていることが多いです。
- 高いセキュリティレベル
- 大容量のストレージ
- ビジネス向けの各種機能
- 手厚いサポート
専門的な知識がなくても比較的簡単に導入・運用できる点は大きな魅力です。ただし、提供される機能やカスタマイズの範囲はサービスごとに決まっており、IaaSほどの自由度はありません。
メールサーバーをクラウド化する手順
ここでは、メールサーバーをクラウド化するための手順を解説します。以下の流れを参考に、スムーズに移行を進めましょう。
目的を明確にする
まず、メールサーバーをクラウド化する目的をはっきりさせましょう。例えば、コストの削減、運用負荷の軽減、リモートワークへの対応など、具体的な目的を設定することで移行先の選定や移行計画を立てやすくなります。
目的を明確にする際は現在のシステムにどんな課題があるのかを洗い出すことも大切です。現状のワークフローで問題となっている部分を特定し、クラウド化で解決できる課題や改善点を整理しましょう。情報システム部門だけでなく、実際にメールシステムを使う各部署の担当者からもヒアリングを行うと、より実態に即した要件定義ができます。
移行先を選定する
明確にした目的をもとに、IaaSを利用するかクラウドメールサービス(SaaS)を使うか、移行先を検討します。比較する際のポイントは次の通りです。
機能面
ビジネス向けメールサーバーには、自動送信機能、メーリングリスト、スパムフィルター、誤送信対策など、多様な機能があります。サーバーやプランによって搭載される機能は異なるため、あらかじめ必要な機能を整理することが大切です。無料トライアルを活用すれば、機能だけでなく操作性も確認でき、自社に合っているか総合的に判断できます。
コスト面
IaaSもクラウドメールサービスも、多くがサブスクリプション型の料金体系を採用しています。高性能なほど料金は高くなる傾向があるため、性能とコストのバランスを考えることが重要です。例えば、社内のやり取りだけでなくマーケティングにも活用する場合は、大容量かつ多アカウントに対応できるサーバーが適しているでしょう。サービスによっては、プランやアカウント数で大きく料金が変わるため、正確なコスト試算が必要です。公式サイトの料金表だけでなく、1ユーザーあたりの費用を算出して比較すると、コストパフォーマンスを把握しやすくなります。
セキュリティ面
クラウド化ではデータを社外に保存することになるため、ベンダーのセキュリティ対策をしっかり確認することが重要です。ベンダーが運営するデータセンターのセキュリティ体制や、サービスが提供する各種セキュリティ機能を比較検討しましょう。
移行準備・データ移行
移行先が決まったら、データ移行の準備を始めます。まずは、自社のメール環境を把握することが重要です。
- メールアカウントの数
- 各アカウントのメールデータ容量
- DNS設定内容
- 使用しているプロトコル(IMAP/POP/SMTP など)
メールデータが多かったり設定が複雑だったりする場合は、データ移行ツールの利用がおすすめです。クラウドサービスによっては、専用の移行ツールを提供していることもあります。
また、万一に備え移行作業を始める前に現行のメールサーバーの全データを必ずバックアップしておきましょう。準備が整ったら、実際にデータを移行します。
切り替え
移行が完了したらDNSに登録している情報を新しいクラウドメールサーバーへ切り替えます。具体的にはドメイン宛てのメールをどのメールサーバーへ配送するかを指定する MXレコードの変更です。
MXレコードを新しいクラウドメールサーバーのアドレスに書き換えることで、メールの配送先が切り替わります。ただし、MXレコードの反映には数時間から最長72時間ほどかかる場合があります。この間、新旧両方のサーバーにメールが届くこともあるため注意が必要です。業務への影響を最小限にするためには、以下のような対応がおすすめです。
- 業務時間外や休日に切り替え作業を実施する
- 切り替え後すぐに送受信テストを行う
- 問題がなければ旧サーバーを段階的に停止する
新しいクラウドメールサーバーへの切り替えが安定したら、最終的にデータのバックアップを取得し、旧サーバーを完全に停止します。
メールサーバーのクラウド化とメールリレーサービスの関連性
企業のITインフラにおいて、メールサーバーのクラウド化は運用負荷の軽減やコスト削減、リモートワーク対応など多くのメリットをもたらします。しかし、クラウドサービスだけでは大量メール配信時の「配信遅延」「到達率低下」「スパム判定」などの課題が完全に解消されるわけではありません。
特にメールマーケティングや通知メールなど、一度に大量のメールを確実に届ける必要がある場合、クラウドメールサービスの標準機能や送信制限では不十分なケースが多くなります。このような課題を補完し、安定した大量メール配信を実現するために注目されているのが「メールリレーサービス」です。
メールリレーサービスとは
メールリレーサービスは、送信元サーバーと受信先サーバーの間に中継サーバーを設け、メールを一時的に預かり最適なタイミングと方法で配信する仕組みです。主な特徴・メリットは以下の通りです。
- サーバー負荷の分散
大量メール送信時の自社サーバー負荷を軽減し、安定した配信を実現。 - 高い到達率
専用の配信インフラと認証技術(SPF/DKIM/DMARC等)により、迷惑メール判定やブロックを回避しやすい。 - 配信速度の最適化
リレーサーバーが最適な送信タイミングを自動調整し、遅延や未達を防止。 - 配信結果の可視化
送信エラーや到達状況などの詳細なレポートを取得でき、問題の早期発見・改善が可能。 - セキュリティ強化
暗号化通信や認証機能を標準搭載し、安全なメール配信をサポート。
おすすめのSMTPリレーサービス「ブラストエンジン」

ブラストエンジンは、SMTPリレーサーバーを使用して、簡単に大量のメールを高速配信することが可能です。さらに、メールサーバーを必要とせず、API経由でメールを送信する仕組みも提供しています。
ブラストエンジンは、サーバーの運用やメンテナンスを行っているため、常に高いIPレピュテーションを維持しながら、安全にメールを送ることができます。
以下のような課題がある場合は、ブラストエンジンの利用を検討してみることをおすすめします。
- 自社のIPアドレスやドメインがブラックリストに登録されていて、メールが届かない場合
- 国内キャリアにメールが届かず、対応方法がわからない場合
- 自社でメールサーバーを管理・運用したくない場合
また、ブラストエンジンは各メールプロバイダーや携帯キャリアのドメインに最適化されており、大規模なネットワークを経由してメール配信を行うことで、日本国内での到達率を圧倒的に高めています。
利用料金は月額3,000円からとコストパフォーマンスにも優れており、メールだけでなく、日本語での電話サポートにも対応しています。メールアドレスの入力のみで無料トライアルが可能ですので、まずは気軽にお試しください。
まとめ
「メールサーバーをクラウド化」することは、企業にとって大きな変化ですが、その分多くのメリットを享受できます。運用負荷の軽減やコスト最適化、リモートワーク対応の強化など、ビジネス環境の変化に柔軟に対応できるのは大きな魅力です。
ただし、クラウド化にはデメリットやリスクも存在します。特にコストの増大や自由度の制限、ベンダー依存によるセキュリティ面の懸念などを十分に理解した上で、移行計画を立てることが重要です。
本記事で解説したように、クラウド化を成功させるためには以下の3つが欠かせません。
- 自社の目的を明確化すること
- 移行先の選定ポイントを把握すること
- データ移行の準備と計画を入念に行うこと
企業にとって「メールサーバーをクラウド化」する決断は、単なるシステム移行に留まらず、経営戦略そのものに直結する大きなテーマです。ぜひこの記事を参考に、御社にとって最適なクラウド化の道筋を見つけてください。