クラウドサーバーとは?仕組み・料金相場・比較ポイントまで初心者にもわかりやすく解説
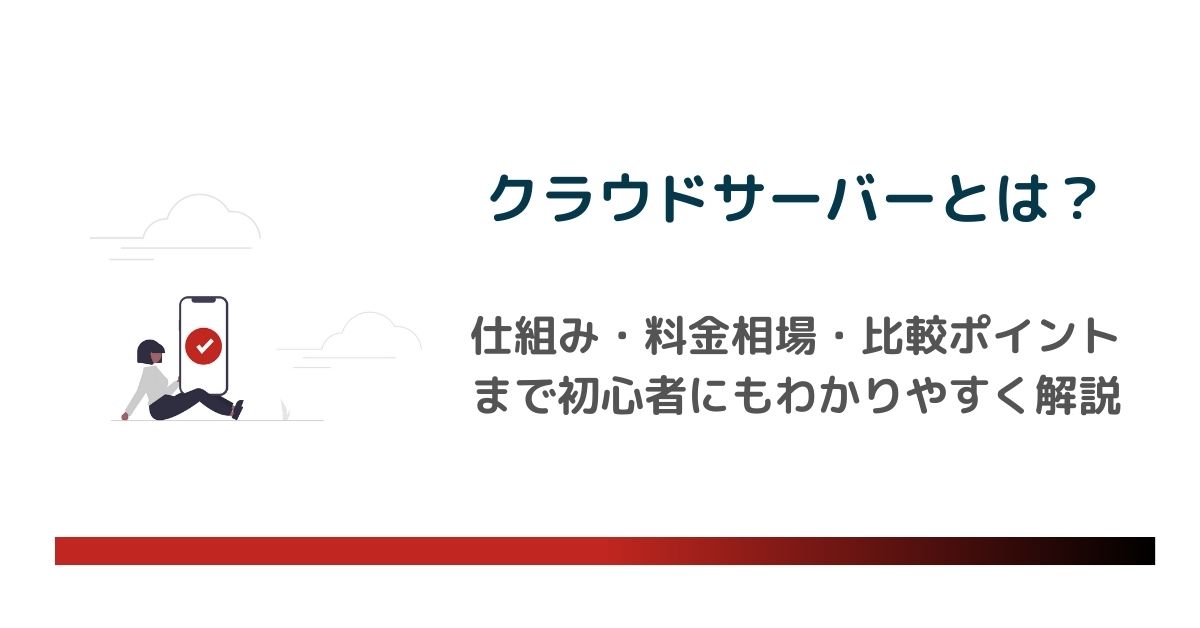
クラウドサーバーという言葉を聞いたことがあるけれど「実際どういうものなの?」「自社に導入すべきか判断できない…」と感じている方は多いのではないでしょうか。
クラウドサーバーは従来の物理サーバーとは異なり、インターネット上で仮想的に構築・利用できるサーバーです。サーバーを所有・管理する必要がなく、必要なときに必要な分だけリソースを使えるのが最大の特徴です。そのため、スタートアップから大企業まで、さまざまな企業が業務効率化やコスト削減を目的にクラウドサーバーを導入しています。
とはいえ、クラウドサーバーにはIaaSやPaaSといった分類があり、料金体系やサービスの特性も異なります。また、処理性能やセキュリティ、拡張性、サポート体制など、選定にあたって押さえておきたいポイントも多数あります。
本記事ではクラウドサーバーの基本的な仕組みから、料金相場、主なサービスの比較ポイントまで、クラウド導入を検討している方にとって必要な情報を網羅的にわかりやすく解説します。クラウドサーバー選びで後悔しないために、まずは基礎知識からしっかり理解していきましょう。

クラウドサーバーとは
クラウドサーバーとはインターネットを通じて利用できる仮想的なサーバーのことです。仮想サーバーとは1台の物理サーバー上で複数のOSを同時に動かし、それぞれを独立したサーバーとして扱える仕組みを指します。
クラウドサーバーはCSP(Cloud Service Provider)と呼ばれる事業者が提供しており、アカウントとインターネット環境さえあれば、いつでもどこからでもアクセス可能です。このクラウドサーバーは大きく分けて以下の2種類に分類されます。
- IaaS(Infrastructure as a Service)
仮想サーバー、ストレージ、ネットワークといったインフラ環境を提供するサービス - PaaS(Platform as a Service)
アプリケーション開発や実行に必要な環境(OS、ミドルウェアなど)を提供するサービス
クラウドサーバーのメリット
ここからは、クラウドサーバーを導入することで得られる代表的なメリットを紹介します。
コストを抑えられる
物理サーバーではサーバー本体や周辺機器の購入、ネットワーク環境の構築に加えて、保守・監視などの人手も必要になります。構築だけで数十万円、さらに毎月の運用費として構築費用の10〜15%がかかることも珍しくありません。
一方でクラウドサーバーでは機器の購入が不要であり、基本的な保守や監視はCSP側が担当します。さらに、従量課金制のサービスが多いため「使った分だけ」支払えばよく、ムダなコストを抑えやすいのも大きな特徴です。
拡張性が高い
クラウドサーバーは必要に応じてすぐに性能や容量を変更できる柔軟さが魅力です。物理サーバーのようにストレージを物理的に追加したり、新しい機材に移行したりする必要はありません。以下のような状況でもスムーズに対応できます。
- アクセス数が急増したとき
- 新しいサービスの展開でリソースが必要になったとき
- 利用しなくなったリソースを削減したいとき
また、オートスケール機能が用意されているクラウドサービスでは負荷に応じて自動的にリソースを拡張・縮小できるため、常に最適な状態で運用できます。
導入に時間がかからない
物理サーバーの場合、発注から構築、稼働までに数週間〜数か月かかるケースもあります。一方、クラウドサーバーはすでに完成されたインフラを利用するため、最短で30分〜1時間ほどでサービスを開始できることもあります。
とくにパブリッククラウドなら申込みから即利用が可能で、スピード感のある事業展開を後押ししてくれます。
障害に強い
クラウドサーバーはCSPが複数のデータセンターでサービスを提供しており、リソースやデータを分散して管理しています。そのため、どこか1つのデータセンターで障害が起きても、他の拠点からサービス提供を継続できる仕組みになっています。
また、レンタルサーバーと比べても負荷の分散や自動バックアップの仕組みが整っているため、サーバーダウンのリスクも低く大規模障害にも強い設計がされています。
BCP対策として有効
BCP(Business Continuity Plan)とは災害やテロなどの非常時に事業継続を可能にするための計画のこと。クラウドサーバーは、耐震性や防火・停電対策の整ったデータセンターから提供されているため、緊急時にもデータを安全に守れる可能性が高くなります。
加えて、クラウド事業者が高度なセキュリティやバックアップ、障害対応を行っているため、自社で大がかりな対策を施さなくても安心して利用できる点もメリットです。
クラウドサーバーの例
ここでは、クラウドサーバーを提供している主要なサービスを紹介します。代表的なものとしては、「Amazon EC2」「Virtual Machines(Microsoft Azure)」「Compute Engine(Google Cloud)」などがあり、いずれも世界中の多くの企業で利用されています。
Amazon EC2(AWS)
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute Cloud)はAmazonが提供するクラウドサービスの一つで、AWS(Amazon Web Services)に含まれています。ユーザーはさまざまなOSやスペックの仮想サーバーを自由に構築・管理できるのが特徴です。
また、AWSは世界中にデータセンターを持っており、パフォーマンス面でも法的要件への対応でも柔軟性があります。冗長化構成も組みやすく災害時の事業継続(BCP)にも有効です。
料金は従量課金制を基本とし、利用目的や期間に応じて選べる複数のプランが用意されています。
以下は代表的な料金プランの概要です。
- オンデマンドインスタンス
必要なときに必要なだけ使える従量課金制プラン。時間または秒単位で課金され、前払い・長期契約は不要です。 - リザーブドインスタンス
1年または3年単位でリソースを予約することで、大幅な割引が適用されるプラン。定額制で、一部または全額を前払いすることでさらに割引を受けることができます。 - スポットインスタンス
AWSの未使用リソースをオークション形式で利用するプラン。割安ですが、リソースが不要と判断された場合には停止・削除される可能性があります。 - Savings Plans
一定期間(1年・3年)の間に支払う金額を事前に決めることで、オンデマンド利用よりも割引が受けられる柔軟なプラン。ただし、実際に利用しなくても、事前に設定した金額は支払う必要があります。
※なお、Amazon EC2ではサーバー稼働中の通信(データ転送)にも料金が発生するため、全体のコストを見積もる際には注意が必要です。
Virtual Machines(Microsoft Azure)
Virtual MachinesはMicrosoftのクラウドサービス「Azure」で提供されているクラウドサービスです。11種類の仮想マシンが用意されており、高い拡張性と優れたセキュリティ性を持っています。
また、Virtual Machinesは分単位で課金される従量課金制ですが、予約する場合や開発・テスト環境として利用する場合は割引を受けられます。仮想マシンの種類とそれぞれの料金は以下の通りです。料金はアメリカ合衆国ドルとなっています。
| シリーズ | 開始価格(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| Aシリーズ | $11.68 | 開発やテストに適している |
| Bsシリーズ | $3.80 | コストパフォーマンスに優れている |
| Dシリーズ | $41.61 | 汎用的でバランスが取れている |
| Eシリーズ | $58.40 | メモリに最適化されている |
| Fシリーズ | $35.77 | CPUに最適化されている |
| Gシリーズ | $320.47 | Dシリーズの2倍のメモリと4倍のSSDが搭載されている |
| Hシリーズ | $581.08 | 高度な計算処理を必要とするアプリに最適化されている |
| Lsシリーズ | $455.52 | ストレージに最適化されている |
| Mシリーズ | $1,121.28 | 大量のメモリが必要なアプリに最適化されている |
| Mv2シリーズ | $16,286.30 | Mシリーズでも最も大きなメモリを搭載している |
| Nシリーズ | $657 | GPUを搭載している |
Compute Engine(Google Cloud)
Compute EngineはGoogle Cloudで提供されているクラウドサービスです。要件に合わせてサーバー環境を構築でき、高いセキュリティ性も持っています。また、Googleが提供する他のサービスとの統合やオートスケールの利用も可能です。
さらに、メンテナンス時や障害発生時に稼働中の仮想マシンは別のサーバーに自動的に移行するため、ストレスなく運用できます。サーバーの利用料金は秒単位で課金される従量課金制で、ストレージの料金は保存データ量に基づいて計算されます。提供されている主なマシンタイプの種類は以下の通りです。
| マシンタイプ | 備考 |
|---|---|
| C4 | 高いパフォーマンスを発揮するマシン |
| C3 | 高いパフォーマンスを発揮するマシン |
| C3D | 高いパフォーマンスを発揮するマシン |
| N4 | バランスの取れた価格と性能を持つマシン |
| N2 | バランスの取れた価格と性能を持つマシン |
| N2D | バランスの取れた価格と性能を持つマシン |
| N1 | バランスの取れた価格と性能を持つマシン |
| E2 | 価格の低さが特徴のマシン |
| Tau T2D | 分散処理に最適化されたマシン |
| Tau T2A | 分散処理に最適化されたマシン |
| Z3 | ストレージに最適化されたマシン |
| H3 | 負荷の高い処理に最適化されたマシン |
| C2 | 負荷の高い処理に最適化されたマシン |
| C2D | 負荷の高い処理に最適化されたマシン |
| X4 | 大量のメモリが必要な処理に最適化されたマシン |
| M3 | 大量のメモリが必要な処理に最適化されたマシン |
| M2 | 大量のメモリが必要な処理に最適化されたマシン |
| M1 | 大量のメモリが必要な処理に最適化されたマシン |
| A3 | 複雑な計算やデータ処理に最適化されたマシン |
| A2 | 複雑な計算やデータ処理に最適化されたマシン |
| G2 | 複雑な計算やデータ処理に最適化されたマシン |
クラウドサーバーの料金相場
クラウドサーバーは一般的に従量課金制で提供されており、利用した分だけ料金が発生する仕組みになっています。料金は主に、アクセス量やCPU、メモリ、ストレージなどのサーバースペックによって変わってきます。
おおよその相場としては初期費用が0〜10万円、月額料金はおおよそ3万円前後とされています。ただし、サービスによっては通信量やストレージ使用料が別途かかることもあるため、導入前に料金体系をよく確認することをおすすめします。
クラウドサーバーの比較ポイント
クラウドサーバーを選ぶ際には単なるコスト比較だけでなく、さまざまな観点から検討する必要があります。ここでは、選定時にチェックしたい主なポイントを紹介します。
処理速度・処理能力
業務用途でクラウドサーバーを使う場合、高速で安定した処理性能が重要です。処理能力が不足していると業務の遅延やWebサイトの表示遅延につながり、ユーザーの離脱や検索順位の低下にもつながる可能性があります。確認しておきたいポイントは以下のとおりです。
- CPUの性能
- メモリの容量
- データ転送速度(ネットワーク帯域)
これらが自社の用途に見合っているかどうかをチェックしましょう。
用途に適しているか
クラウドサーバーにはIaaSとPaaSの種類があり、それぞれ得意とする用途が異なります。例えば、IaaSはWebサイト運営やアプリケーション開発に適していますが、テスト開発やデータ分析にはPaaSの方が向いている場合があります。また、クラウドサーバーは以下のようにベースとなる環境の違いもあります。
- ブラウザベース
ファイル共有がしやすいが、拡張性は低め - Windowsベース
操作性に慣れている人が多いが、ライセンス費用がかかる - Linuxベース
拡張性が高く、コストを抑えやすいが、専門知識が必要
それぞれの特徴を踏まえて、自社のニーズに合ったものを選びましょう。
セキュリティ対策
クラウドサーバーを利用するということは機密情報や個人情報などの大切なデータを外部事業者に預けるということです。サービス提供会社(CSP)のセキュリティ対策が不十分だと、情報漏えいなどのリスクが高まります。
不正アクセスや未許可通信を防ぐファイアウォールや通信の暗号化が施されているかどうか、また、データセンター自体の物理的な安全性や運用体制なども確認しておくと安心です。
拡張性の高さ
事業の成長や繁忙期のリソース増加に対応するためには拡張性の高いクラウドサーバーを選ぶことがポイントになります。必要なときにリソースを増減できるか、オートスケール機能に対応しているかなどを確認しましょう。
なお、リソースの増減には上限が設定されている場合もあるため、将来の拡張計画も見据えたチェックが必要です。
サポート体制
サポート体制もクラウドサーバー選びの重要なポイントです。トラブル発生時やデータ移行時に十分な支援が得られるサービスであればダウンタイムのリスクやデータ損失を最小限に抑えることができます。例えば、以下の点をチェックすると安心です。
- サポート対応の時間帯(24時間365日かどうか)
- 問い合わせ手段(メール、電話、チャットなど)
- 対応スピードやサポートの質
クラウドサーバーとレンタルサーバーの違い
クラウドサーバーとよく比較されるのがレンタルサーバーです。どちらもインターネットを通じてサーバーを利用できる点では共通していますが、用途や自由度、料金体系には大きな違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を比較し自社に合った選択ができるよう解説します。
自由度と拡張性の違い
レンタルサーバーは既に構成された環境を貸し出すサービスで、サーバー設定やインストール可能なソフトウェアに制限がある場合が多いです。一方、クラウドサーバーは自分でOSやアプリケーションを選んで構築できるため、自由度が高く構成のカスタマイズが可能です。
また、クラウドサーバーは契約後すぐにスペックを変更できるスケーラビリティを持ち、急なアクセス増加や事業拡大時にも柔軟に対応できます。レンタルサーバーではこのような即時対応は難しく移行作業が必要になることがあります。
安定性と障害時の対応の違い
クラウドサーバーは複数のデータセンターや分散構成によって高い可用性が保たれており、万が一障害が発生しても他のサーバーへ切り替えることでサービス継続が可能です。
一方、レンタルサーバーでは物理サーバー1台に依存する構成が多いため、障害時には復旧までの時間がかかるリスクがあります。BCP(事業継続計画)を意識する企業にとってはクラウドサーバーのほうが安心できる選択肢といえるでしょう。
まとめ
クラウドサーバーは柔軟性や拡張性、コスト面で多くのメリットを持つサービスです。自社の目的や業務規模に合ったクラウドサーバーを選ぶことで、業務効率の向上やインフラ運用の最適化につなげることができます。
導入前には料金体系やサーバー性能、セキュリティ対策、サポート体制などをしっかり比較し、長期的な視点で選定することが大切です。特に初めて導入を検討している方は今回紹介した比較ポイントをもとに、自社にとって最適なサービスを見極めてください。



